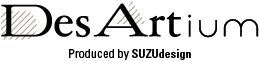『ティファニーで朝食を』 ~奔放なパリピ女子が行き着く先は、愛か金か ~


タイトルに憧れて、なんとなく観賞してみたくなる女性は多いのではないか。
ただ注意して欲しいのは、存分にティファニーのジュエリーが拝める! などというきらめきいっぱいの作品ではない。それを期待してしまうと、この映画が持つ本来の持ち味が削れてしまうどころか、稀に謎の酷評に繋がる。
田舎から逃げ出してきた若い娘が、干渉を嫌い、自由とお金を愛し、大都会ニューヨークでセレブの出入りする世界に足を運び、おこぼれをもらって生活しながら、大富豪との結婚を目論む。しかしながら時折、そんな自分が嫌になる。皮肉にも、現代東京でも似たような現象があるので、ある層にはリンクする映画なのではないかと思わずにはいられなかった。
良くも悪くも、1960年代といった古い価値観とその時代設計が盛り沢山。男性の女性に対する恋愛観や、アジア人に対するイメージ、やや薄弱な倫理観など。まぁあまり細かいことは気にせず、「こういう感じだったんだなぁ、時代だなぁ」と制作当時の歴史を楽しみつつ、ひとつの作品としてフラットな目線で観賞すると良いかと。
あらすじと作品の概要
<あらすじ>
夜明けのニューヨーク、黒のドレスに身を包むホリー(オードリー・ヘプバーン)が、五番街の一等地に構えるティファニー本店のまだ開店前のショーウィンドウの前で、ホットコーヒーとデニッシュを食すシーンから始まる。彼女いわく、「赤く気分が落ち込むときはティーファニーヘ行く」という。
名前のない猫と2人きりで暮らしているアパートの上階に、ある日、ポールという小説家の卵が引っ越してきた。彼は、室内装飾家の女性と愛人契約を結んでおり、金で囲われた身。一方のホリーも、夜な夜なパーティーへ繰り出しては、セレブな男性相手に報酬をもらう娼婦のような生活をしていたことから、似た者同士の感情をお互いに持ち、友人関係を育んでいく。
やがてポールが小説家としての芽が出始めたころ、ホリーの複雑な過去や心の弱さを知らしめる出来事が…
| 原題 | Breakfast at Tiffany’s |
|---|---|
| 制作国 | アメリカ |
| 公開年 | 1961.10(USA)|1961.11(JP) |
| 上演時間 | 115分 |
| 監督 | ブレイク・エドワーズ |
| 脚本 | ジョージ・アクセルロッド |
| 登場人物(キャスト) |
・ホリー・ゴライトリー(オードリー・ヘプバーン) ・ポール・バージャク(ジョージ・ペパード) ・2E[室内装飾家でポールのパトロン](パトリシア・ニール) ・ドク・ゴライトリー[ホリーの夫](バディ・イブセン) ・ユニオシ, I.Y.(ミッキー・ルーニー) ・ホセ・ダ・シルヴァ・ペレイラ(ホセ・ルイス・デ・ヴィラロンガ) ・O.J.バーマン(マーティン・バルサム) ・サリー・トマト(アランリード) |
ストーリーの見どころを追う

本項目は物語の核心やラストの展開に触れているため、ストーリーの確認をされたい方に適しています。「まだ映画観てない」という方は 次項 へ飛んでください。
幕開け直後、スンと冷えたひと気のない夜明けのニューヨークがカットインする。五番街のティファニーの前にタクシーから降り立った、細身のリトル・ブラック・ドレスを身にまとい、デニッシュとホットコーヒーを手にした美しい女性が、ショーウィンドウに向かってゆっくりと歩いていく。BGMには『Moon River』—。
最高なのである。
女性の憧れがぎゅっと凝縮されたオープニング2分半の映像は、『ティファニーで朝食を』のタイトルを背負う幕開けにふさわしかった。
たまに評価の低いレビューで「タイトル通りなのって最初だけで終わりじゃん!」と書かれているのを見かけるが、まったくそんなことはないのでちゃんとストーリーに入り込んで観て欲しい。
1960年代の古い映画で、時代設計や価値観は異なりつつも、
<パーティーガールや時に娼婦として、セレブと時を共にすることにより報酬を得て生活をする若い女>と、<金持ちの年増女性に金で囲われてた、なかなか芽の出ない小説家気取りの青年>といった、端から見れば経済的に自立できていない(誰かに依存していないとままならない)若者たちの人間模様
という、現代でも普通にあり得る光景を、この映画では非常にソフトに描いているので、共感しながら観賞出来るのではないかと思う。
この、“非常にソフトに描く” というのがミソで、本作品は人間の汚い部分や嫌らしい部分を省いて制作しているようだ。
なので全編を通して安心して観れることはもちろん、「いわゆるオシャレ映画」、「オードリー のイメージビデオ」と揶揄されるのも頷ける。
それが功を奏し、だからこそ肩肘張らずに、年代を超えて長く愛されている映画であり、時間を空けて年齢の節目で何度でも観たいと思える作品なのだろう。
劇中前半、ホリーが初対面のポールに向かって、ひとりごとのようにつぶやいた言葉、
ホリー:
「私は気分が赤く気分が沈むの。つらいわ、原因不明なんだから 。そんな時は、タクシーでティファニーへ行くの。そんな静かに澄ましたところ。そんなところに住みたいわ。」
とても素敵な表現なので、本作品の中でお気に入りのシーン。
金持ちに依存する生活から抜け出すべく、セレブ相手に婚活をする日々に疲れながらも、自由奔放に生きている現状も手放したくはないジレンマ。だけど時間は残酷にも後ろからぴったりと追いかけてくる焦燥感。
誰でも辛いときや悲しいとき、ストレスを解消したいときの “拠り所” があると思うが、ホリーにとっての拠り所がティファニーだということ。
いまだ何者でもない、誰のものでもない自分だからこそ、飼い猫には名前をつけず、部屋には家具をほとんど置かず必要最低限で済ませ、スーツケースに物を詰めていつでも立ち去れるような暮らしぶりをしているのだ。
やがて、1人の初老の男がホリーたちの住むアパートの前に現れる。
ホリーを迎えにきた彼女の夫だ。
ホリーと対面する前に、ポールが夫の対応をするのだが、この2人のやりとりや会話の内容は注視したい。この前後の物語とホリーの人となり(人と心の距離をとりたがり、情緒不安定さが垣間見れ、金持ちとの結婚を狙う理由)を言語化するいわゆる “布石” 的役割があるシーンだからだ。
ここでホリーの貧しい過去や、彼女の本名が “ルラメー” だということ、実はその男と結婚しており、前妻との間に生まれた4人の子供たちとテキサスで暮らしていたという事実をポールは知らされる。
さらに、このときに食べていたコーンキャンディのおまけのリングが、のちに出てくるので覚えておこう。
友情が愛情へと変わるとき
それはそうと、この小説家のポール、だんだんと友情以上の感情をホリーに対して抱くようになる。それはホリーもおそらく同じタイミングで。
それが如実に表れるのは、ホリーと2人で「今までやってこなかったことをしちゃおうNYデート」をしたあとだろう。ティファニーに入店しジュエリーを買おうとしたが予算が足りず、おもちゃのリングに刻印をしてもらったり、図書館に寄贈されたポールの書籍に勝手にサインを書いたり、おもちゃ屋で万引きをしたり…(現代の感覚で考えたらとんでもない)
甘く刺激的な1日を過ごしたことにより、2人の心の距離がぐっと近づいたのがスクリーンから感じとれる。
その日の翌朝、ポールはパトロンの2Eに他の女の影を追求され、相手はどんな金持ち女なのかを詰められた際、
ポール:
(僕が)援助(をしてもらう)どころではない。逆に僕の助けが必要な人だ。
と、口にした。2Eと別れたい(愛人契約を切りたい)旨も。結局は大人の女の掌の上で転がされ、うやむやにされてはいたが…
一方ホリーはというと、他人と損得勘定なしで愛し愛される関係になることにとてつもない恐怖を抱いているのだ。
金と地位と名誉だけでしか人を推し測れず、その相手を自身の価値のバロメータとしているホリーは、まるでポールを排除するかのように、ブラジルの富豪ホセと早々に婚約(厳密に言うとそれ未満だが)をしてしまう。
そんなホリーの胸の内を知らないポールは、ティファニーに刻印を依頼していたおもちゃの指輪を取りに行った足で、図書館にいたホリーに愛の言葉を告げたのだ。上述のような感情に陥っていたホリーは、当然それを突っ撥ねることになる。
ホリーの口から「ネズミ」と言う言葉がたびたび発せられる。
彼女いわく、自分のことをただ女として消耗し、報酬を渡してくるような男は「薄汚い特級ネズミ」だと言う。「ネズミ」ではないのはポールと、彼女の元夫と、婚約者のホセだけだそうだ。
しかしそのホセも、ホリーが麻薬密売人と面会していた事実を疑われ逮捕されると、掌を返したように最後の手紙で
ホセ:
(今回のホリー逮捕は)私の地位に似つかわしい妻としてあるまじき事だ。〜 家名を汚すことはできない。私のことは忘れてくれ。
と残し去っていった。
ラストのタクシーのシーンは物語のクライマックスだ。
ホリーが釈放されたあとのシーンなのだが、上述のホセの手紙もラストのタクシーの中で読まれている。
元々、複雑な過去を持つゆえに情緒不安定なホリー。やっと手にしたと思っていた理想の幸せが自分の手から離れてしまったことで、自暴自棄になってしまう。破れかぶれに
ホリー:
「このまま空港へ。ブラジルへ行くわ。ホセなんかを追いかけるんじゃない。変な事で名前も知られちゃってるし、この街には用はないの。ブラジルのお金持ち50人の名簿を作ってもらって」
と無茶苦茶なことを次から次へと発するホリーを、厳しくも優しく見つめるポールの瞳に彼女は気づいていたのだろう、彼を直視することができないのだ。
そしてこのあとのポールの熱い言葉で彼女の従来の価値観に一石を投じるのだが、ひょっとしたら、このセリフはまた現代を生きる女性からしたら一部賛否両論出るかもしれない。
ポール:「僕は君を愛している。君は僕のものだ」
ホリー:「檻に入るのはお断りよ」
ポール:「檻じゃない。愛だろ」
ホリー:「この猫と同じ名無しよ。誰のものでもない。ひとりぼっちなのよ」
〜
ポール:「君には勇気がない。人が生きてることを認めない。愛さえもだ。人のものになり合うことだけが幸福への道だ。自分だけは自由の身でいても、生きるのが恐ろしいのだ。自分で作った檻の中にいれば、それはどこにいてもついて回る。自分からは逃げられない」
「僕のものになれ」や「誰かのものになることだけが幸福」といった日本語訳が字幕に流れるが、偏見をぶちかましたいわけではないので、この辺りはあまり深く考えないで欲しい。
要はポールは、「ホリーのことを純粋に愛している」ということと、「自身を傷つけ寂しい思いをするような生き方はもうやめてくれ」と言いたいわけだ。多少彼は口下手であることと、あまりにも英文そのまんま直訳してしまうというセンスの成果であろう。
ところで、ポールがこのようにホリーの心に踏み込むのを後押ししたきっかけというのが、実はおもしろいところに転がっていたのを見逃しはしていないか。
ホリーが逮捕され、程なくして釈放されたのには裏で手を回していた人物がいたからだ。それは、芸能プロダクションのドン:O.J.バーマン氏(ホリーの部屋でのパーティーシーンで一度出ている)である。彼はロサンゼルスでホリーを拾い、色々と身の回りの世話(それこそ “いろんな意味で” だろう)をしていた男だ。そして、今回の事件で弁護士を用立て、保釈金を匿名で用意し、いったんホテルで身を潜めよと助言してくれた人物。
釈放前夜、彼はポールとこの件で電話をしている。ポールの感謝の言葉を受けたそのとき、バーマン氏はこう話したのだ。
O.J.バーマン:
「浮世の義理さ。役に立ったしな。だがあの娘は、イカれとる。偽物だ。だが、本物の偽物だ。意味わかるか?」
「長年世話をし、ここまで育ててきた娘だ、最後まで面倒を見たまで。(あとは頼んだ)」というニュアンスを感じられた。
以下はあくまでも個人の感想だが、ここで彼の言った “本物の偽物” というのは、彼女は欲と金にまみれ薄汚れた裏の世界は似合わないし、居てはいけない人間という意味に捉えた。ポールも、彼女に対してふわふわとそう感じはいたが、おそらくホリーとそれなりの信頼関係が培われていたのであろうバーマン氏に言語化されたこのとき、確信に変わったのだと思う。そうして、クライマックスの車内での会話へとつながっていくのだろう。
さて、今まで自分の前に現れたことのなかった心の綺麗な青年との出会いを経て、真っ直ぐで淀みのない思いを受け取ったホリーに気持ちの変化はあったのだろうか。Moon Riverの流れるラストをぜひ観てみて欲しい。
それにしても、女性が失恋し弱っているときに、真っ直ぐな愛の言葉を告げ、女性がその愛を受けるのを躊躇していると、弱い部分を包み込むような核心をつく言葉を言い放ち、思い出のプレゼントを渡してスッと去るこの手法—。男性陣へ、どうか悪用はしないように。
オードリーの美しさを堪能する

『ティファニーで朝食を』にまつわる逸話で有名なのが、実は主演はオードリーではなくマリリン・モンローで考えられていたということ。そんな話を聞けば確かにそちらも興味が湧くが、原作未読の私が勝手な想像をする限りでは、モンローがホリー役にキャスティングされていたとしたら結構生々しい作品に仕上がるのではないかと思う。
オードリーの、可憐で天真爛漫でそれでいて儚げで、わがままな部分もかわいらしいから許せちゃう… といった感覚を視聴者に与えられたのはかなり強い。そして、娼婦の役とはいえオードリーの上品さが醸し出されていることから、極力いやらしさや生々しさを画面やストーリーから排除し、雰囲気を大事にしたラブロマンス作りを目指したのだろう、とうかがえる。
さて本作品、見どころのひとつはなんといってもオードリーのファッション。

細身のLBD(リトル・ブラック・ドレス)に身を包み、立体的な金メッシュの入った髪をフレンチ・ツイスト(いわゆる夜会巻き)で高めにまとめ、存在感のあるジュエリーをあしらう—。これは、作品冒頭約3分間に現れるオードリーの扮したホリー、そして映画のキービジュアルにもなっている。半世紀以上もの間、世の女性が愛してやまないファッションアイコン的スタイルだ。
ホリーは、パーティーへ赴く際や富裕層の男性と逢引をする際には決まってLBDを身に付けていた。いわゆる彼女の勝負服であり、制服であり、武装スタイルだったのだろう。
実は歴史は意外と浅く、ココ・アヴァン・シャネルが自身のブランドでモードファッションアイテムとして確立させたのが1926年。それまでは、黒一色の服は喪服として認識されていたものだった。
作中でオードリーが着用しているドレスは、ジバンシィブランドのもの。
ポールとホリーがNYの街をデートするシーン(作品中盤)で着用している目の覚めるような朱色のコートも印象に残る。1960年代のファッションは、原色カラーを大胆に取り入れたカラフルさも特徴的だ。このときのホリーは、コートの下にツイード生地のAラインワンピースを着ている。ツイード素材も、シャネルの代名詞と呼ばれていたほどで「シャネルスーツ」といった呼称がついていた。さらに、1960年代に大流行し先駆けとなったミニスカート。当時はミニスカートといっても、膝が出ている丈のものは総じてそう呼ばれていたので、現代の感覚からすると「これがミニスカート?」と不思議に思ったりもする。
また、ポールのパトロンで室内装飾家2Eのファッションも個人的には気に入っている。この時代は原色と相まって、大胆でポップな柄物も流行していた。2Eがポールの家を訪れたときにまとっていた、大きな格子柄のブルーのコートがとても素敵だったし手に入れたくなった。
また、打って変わっていわゆる “着飾っていないオードリー” も必見。
ちょくちょく映し出される部屋着スタイル。細い体に不釣り合いなほどビッグシルエットの白シャツ1枚を羽織り、リゾートビーチのような鮮やかなブルーのアイマスク。そして、タッセル付きの耳栓。こんなかわいい耳栓が当時あったん!?と驚いたものだ。
この2020年の今、『ティファニーで朝食を』を観ても古さをさほど感じないのは、“ファッションの歴史は繰り返す” というのを見て取れるからだろう。「このコーディネートやアレンジ、今やっても全然違和感なさそう!」と学びながら観賞するのも一興だ。
おわりに。
冒頭でも書いたが、1960年代アメリカの時代背景、やや古風な恋愛観だったり、アジア人への偏見、倫理観の欠如など、いちいち気にしていては古い映画は楽しめない。「興味深い! よく世界はここまで変わったものだ」と、感心するくらいにおおらかな気持ちで観てもらいたいと思う。また、思ったよりもひと言ひと言のセリフや、ひとつひとつの挙動や演出が意味をもつ作品なので、ぜひじっくりと観賞して浸ってみて欲しい。
オードリーやタイトルに惹かれて観賞した方が、ひとりでも多くこの作品のピュアな部分やロマンチックさに触れ、感性の肥やしにできますように。
それではまた次回まで。