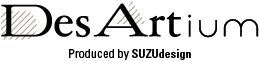『ミッドナイト・イン・パリ』 ~ 色とりどりの顔を持つパリへ誘なわれる夜 ~

本記事は、ところどころで物語の核心やラストの展開に触れているため、ストーリーの確認、登場人物のおさらいをされたい方に適しています。
とても感性の高いアーティストさんが、数年前にラジオで紹介していたのをきっかけに視聴したのがこの『ミッドナイト・イン・パリ』だった。初見から数年経ったが、このご時世で旅行ができないので「せめて旅してる雰囲気だけでも…」といった動機で今回レビューしてみた。
何度でも観たい、観賞するたびに新たな発見がある、個人的には長く楽しめる作品だ。
この映画はできれば雨のシトシトと降る真夜中に部屋を暗くして、白ワイン片手にオリーブでもつまみながら、パリの美しい街並みに酔いしれて、ファニーでロマンチックな時間を旅したい。
あらすじと作品の概要
<あらすじ>
売れっ子映画脚本家の青年ギルは、小説家を目指して処女作を執筆中のさなか、婚約者のイネズとその両親と共にパリへ旅行へ。安定の職を手放してでも夢を叶えたいギルと、いわゆるマテリアルガールであるイネズは、性格や価値観が合わず旅先でも喧嘩ばかり。
ある夜、ギルはイネズと別行動していた折、酒に酔いおまけに道に迷ってしまった。少し休憩をしていたところに、プジョーのアンティーク車が目の前に止まり、乗車している華やかな様子の客人が数名「一緒に行こう!」と酒を片手に手招きしているのだ。わけもわからぬまま車に乗り込み、そのままにぎやかなパーティー会場へと誘なわれたギル。そこは作家ジャン・コクトー主催のパーティーで、作家のスコット・フィッツジェラルドとゼルダ夫妻、音楽家のコール・ポーターと出会い、ここが1920年代のパリであることにうっすらと気づく。
さらにその後、バーでヘミングウェイと知り合い、評論家のガートルード・スタインを紹介してくれるという流れになった時には確信に変わり、スタインのサロンへ趣きピカソと対面する頃には、置かれている状況に感激していた。
ピカソの愛人でありモデルの美しく麗しいアドリアナとの出会いは、時を超えためくるめくロマンスがギルを手招きした瞬間だった。
| 原題 | Midnight in Paris |
|---|---|
| 制作国 | アメリカ |
| 公開年 | 2011.5(USA)| 2012.5(JP) |
| 上演時間 | 94分 |
| 監督 | ウディ・アレン |
| 脚本 | ウディ・アレン |
| 登場人物(キャスト) |
・ギル・ペンダー(オーウェン・ウィルソン) ・イネズ[ギルの婚約者](レイチェル・マクアダムス) ・アドリアナ(マリオン・コティヤール) ・コール・ポーター(イヴ・エック) ・F・スコット・フィッツジェラルド(トム・ヒドルストン) ・ゼルダ・フィッツジェラルド(アリソン・ピル) ・アーネスト・ヘミングウェイ(コリー・ストール) ・ガートルード・スタイン(キャシー・ベイツ) ・パブロ・ピカソ(マルシャル・ディ・フォンソ・ボー) ・サルバドール・ダリ(エイドリアン・ブロディ) ・マン・レイ(トム・コルディエ) ・ガブリエル[アンティークショップの女主人](レア・セドゥ) |
ストーリーの見どころを追う

この作品は冒頭からじっくりと浸りたい。
およそ3分くらいだろうか。ノスタルジックでありながらも軽快なジャズをBGMに、パリの風景が朝から夜にかけて丁寧に、様々な顔をした街並みが情緒的にスクリーンを流れていく。さすがパリ、といったところか、雲ひとつない快晴というシーンはない。
人によっては「冗長すぎる」と思ったりもするかもしれないが、私はこのイントロは、アレン監督の「ほら、パリってこんなに美しいんだ!ロマンチックで本当に素敵だよね。難しいこと何も考えずに、ゆったり楽しんで観てちょうだいよ!」というような、無邪気で粋なメッセージが聞こえてくる気がする。
さて、そんなパリの街並みや観光名所をひとしきり堪能した後に本編が始まるが、主人公のギルがどれだけパリに憧れ、雨降る街並みを愛し、1920年代という彼にとって特別な時代に想いを馳せているか、胸の内を婚約者のイネズに熱く語るシーンが始まる。その舞台はパリから30分、ノルマンディー地方のジヴェルニーにあるモネの庭。水面に張る水蓮が咲き、柔らかな枝垂れ柳が印象的で、絵画《水蓮の池》をすぐさま思い起こさせる。
『ミッドナイト・イン・パリ』を構成するテーマのひとつには、やはりタイムスリップが挙げられるだろう。しかし、本作のタイムスリップの場面はいささか地味に感じるし、油断してたら見逃してしまいそうになる。パリの路地裏の夜道でギルが酔いを冷ましているところに、パーティーへ向かうという旧式のプジョーが現れ、特に画面の効果があしらわれることもBGMが変わることなく車は走り出すのだ。現代の2010年から1920年代へとタイプスリップをする大事な場面だろうに、なんともあっけない。だけど本作のテイストには、いくらタイムスリップの場面だからといって華美な演出をすることもなく、そういう ”なんでもない日常の延長線” であることがとてもよく似合っている。
キーワードは<黄金時代>

綺麗なパリの景色を映し出す作品であるのとともに、「輝く過去に夢を見ること」と「現実という地に足をつけること」の本質にせまっているのが本作の見どころのひとつでもある。
作中に<黄金時代>というフレーズが何度も出てくる。現代と比較し、「あの頃はよかった」「あの時代は○○の世界において絶好期(=黄金期)だった」と、過去や古い時代を懐かしみ羨む思想だ。
イネズの友人カップルたちとベルサイユ宮殿を観光中、ギルがノスタルジックをテーマにした小説を書いているという話から、 “昔は今より優れた時代だったという誤った認識、すなわち現代に対処できない欠陥人間の懐古主義だ” と、イネズの友人であるポールが解説し割と散々なことを言い放つ。婚約者であるはずのイネズも一緒になって加担しているので、ギルがなんだかかわいそうに見えてきてしまう。
とはいえこのギルという男、なかなかに野暮ったく浮世離れしていて、婚約者や友人たちと観光をしていてもGoing My Wayなことを口走ったりする。イネズもそんなギルを小馬鹿にした発言が多い。こんな序盤だが、きっと視聴者の誰もが早い段階で「なんでこの2人惹かれあって、結婚までする仲に…?」と違和感を覚えるだろう。
以下は少し物語のクライマックスに触れるが、ギルがタイムスリップした先の1920年代で出会い恋に落ちたアドリアナは、「今(=1920年代)はスピードが早すぎるし、毎日が騒々しくてややこしいわ」と、自分の生きる時代を憂う。2人で夜道を寄り添っているところに、これまた年代を感じる馬車が2人を迎えにきた。これまで観てきたものから学ぶに、「ああ、またどこか別の時代へタイムスリップするのだろう」と察知する。
タイムスリップした先は、アドリアナが<ベル・エポック>と憧れる1890年代。あるレストランを訪れた際、画家のロートレック、ゴーギャン、ドガと出会う。しかし、芸術界において多大なる功績を残した芸術家であるにもかかわらず、口を揃えてこう話すのだ。
「現代は空虚で想像力に欠けている。ルネサンス期に生まれたかった。あの時代こそ黄金時代だ」
と。
アドリアナの発言やこの一連の会話を聞いて、ギルは「現実世界から逃げていただけだ。そしてそれはいつの時代の人もそうなんだ」と気づくのだ。皮肉にも、自分が好きになった人が自身と同じノスタルジック思想を持っていることを反面教師として、現実の世界に戻り地に足つけて生きていこうと決心する。
芸術面でも非常に華々しく、装飾技術のアール・ヌーボが誕生し様々な建築物や媒体にあしらわれたのも、後にピカソなどによるキュビズムの大きな礎となる<印象派><ポスト印象派>が台頭したのもこの時代であった。
またファッションに関しても、コルセットを外しモードに転換する傾向が現れ始めた頃でもあり、衣装デザインを勉強していたアドリアナが憧れ心酔するのもわかるといえばわかる気がする。
本作に登場した偉人のまとめ
近頃は、歴史に名を残した人物の伝記的映画が続々と制作されたり、著名な作品のリバイバルやリメイクだったり、オマージュした作品が出てくるなど、気軽に過去の人物なり作品なりに触れやすく学びやすい。
ミッドナイト・イン・パリには、その分野では著名ではあるが、あまり芸術に関心のない日本人からしたら「何した人?」というような人物が次から次へと出てくる。それも名前だけ、表面上だけなので、事前に1920年代文学、アートの予備知識を入れると楽しさ倍増することは間違いない。「名前だけはよく聞くあの偉人はこの偉人と交流があったのか」「時代的にこの人たちはかぶっていたのか」、なんていう楽しみ方もまた乙だ。
この項では、作中に人物としてがっつり登場した偉人も、口頭でしか名前の出てこなかった偉人も、ひとまずはここで網羅できるようにひと通りさらってみることにする。
コール・ポーター

ギルがアンティークカーで運ばれた先のパーティー会場で、大勢の客に囲まれながらピアノを弾き語りしている男性がコール・ポーター。非常に多くの舞台や映画の音楽を作詞作曲してきたアメリカ人。この時に歌っている曲は彼の持ち歌で『Let’s Do It (Let’s Fall in Love)』。ギルとは、パーティーを抜け出す車中のシーンで一瞬だけ絡んでいたシーンがあった。
ポーターは第一次世界大戦中の1916年にパリへ移住してきた。同性愛者だったそうだが、ビジネスに強いリンダという女性と結婚。その後には落馬事故で足を怪我するも、妻・リンダの献身的なサポートにより曲作りは継続して行なった。
F・スコット・フィッツジェラルド
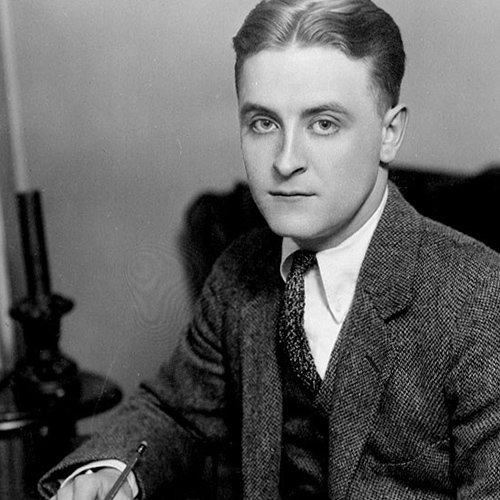
アメリカの小説家。2013年映画化された『華麗なるギャツビー(原題:The Great Gatsby)』の原作者だ。24歳という若さで小説家デビューを果たしたスコット。次に紹介する妻・ゼルダとの出会いもこの頃で、処女作『楽園のこちら側』が無事に出版されたのを機に結婚し、20年代後半には欧州へ移り住んだ。(当時の)アメリカの若者の心情や生活様式、風俗をよくテキストに落とし込めていると物書きとしての評価は高かったが、スコットは一方で、ゼルダの奔放さにつられて毎晩のようにパーティーに繰り出しては散財する日々だったそう。作家のヘミングウェイとは親しい仲である。
ゼルダ・セイヤー・フィッツジェラルド

スコットの妻で、夫婦ともに作家。もともと富裕層であった彼女は大胆不敵で自由奔放。感情の赴くままに行動をする性格からか、嫉妬深く癇癪持ちで、やがて統合失調症を患うとのことで、『ミッドナイト・イン・パリ』の中でも夫を置いて他所の男と飲みに行ったかと思いきや、スコットに女の影があるとなると酒ビン片手に「飛び降りてやるわ!」と橋から身を投げようと自暴自棄になるシーンがあり、なかなかに扱いの難しい人物像で描かれているのがリアルだ。
Amazonプライムにはゼルダの半生を描いたドラマ・シーズン1が配信されているので、興味があればご覧あれ(*続編は制作予定だったが打ち切りになったそうで…残念)。
ジャン・コクトー

上記3名と出会ったパーティーの主催者がこの人物。顔も姿も一切出てこず、ゼルダに「退屈なパーティーよね」と言われた時のみ名前だけ出てきた。フランス人の作家、詩人、劇作家などなど、その才能は多岐にわたって活躍していた。代表作は、アヘン中毒の治療中に執筆した中編小説『恐るべき子供たち』。
アーネスト・ヘミングウェイ

アメリカ生まれの小説家。作中、例のタイムスリップする車内にて戦争のリアルな描写を語るシーンがあるが、スペイン内戦にて軍員を経験しており、作品ジャンルとしては戦争小説を多く執筆した実績がある。代表作は『日はまた昇る』『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』など。
ヘミングウェイは女好きだが、恰幅がよく、硬派で男らしい人物だったそうだ。経済的にも精神的にもスコットを振り回すゼルダを疎ましく思っていたようで、本作の中でも「あの女はだめだ。作家なら執筆に精力を注げ」とスコットに説教をかますシーンが印象的。
ガートルード・スタイン

アメリカ生まれの小説家、評論家であり美術収集家。30歳手前でパリへ移住し、芸術家を集わせるサロンを開設した凄腕のビジネスウーマンだ。映画の中でも、ヘミングウェイがギルを「小説を評価してもらいたいならスタインを紹介する」と言って彼女のサロンまで案内して常連ぶりを表していたり、その場にちょうどピカソが絵を見てもらっていたり、終盤にはマティスがチラッと出演していたり。事実、今でいうとあまりにも有名すぎるアーティストや作家たちが、感性の鋭い彼女の元を訪れていた。著しいアートの発展へと至らせた功労者のひとりとして、確実に彼女は欠かせない人物なのだ。
パブロ・ピカソ

スペイン生まれの芸術家で、制作活動の拠点をパリにおいていた。彼の功績のひとつはキュビズム・ムーブメントを興したことだろう。立体の本質を捉え複数の視点から対象を描くキュビズムという表現法は、絵画はもちろん、音楽や彫刻、建築までにも幅広く影響を与えた大きな芸術活動であった。さらにピカソは市場や時代のニーズを察知し、求められるタッチを顧客に合わせて描き分けていたほどに絵の技術も高く、マーケティングに力も優れ、ビジネスセンスの光る人物だった。それと同時に生粋のモテ男で、浮名の立つ女性は数え切れないほどいたのだそう。
アメデオ・モディリアーニ
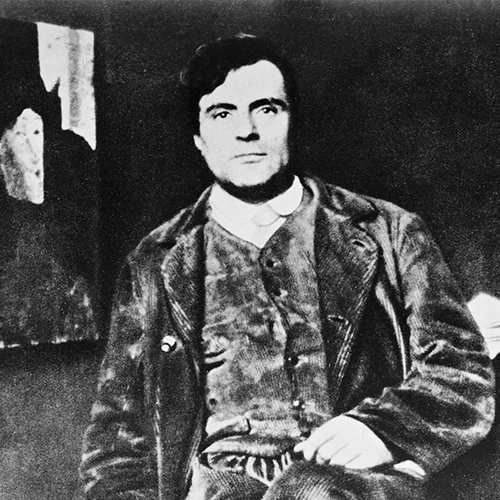
映画の中では、ギルがスタインのサロンでアドリアナと初めて出会った際、アドリアナの身の上話の中で「半年間一緒に暮らしていた」として出てきた名前。ユダヤ系イタリア人画家で、芸術活動はピカソなどとともにパリにて。全体的に縦に長い無表情な女性のポートレートを多く描いてきたが、生前はこの独特なタッチの絵は評価されなかったようだ。持病の結核に苦しみ、酒や薬に依存しており、1920年に35歳という若さで結核性髄膜炎で亡くなった。
アーチボルド・マクリーシュ

アメリカ出身の詩人であり劇作家。パリへ渡り執筆活動に励む前は弁護士をしており、その後晩年まではハーバード大学で教授に就いた。映画中盤、ギルを遊園地でのダンスパーティーに誘ったとして作中では描かれているが、人物としては登場しない。
ジューナ・バーンズ

アメリカ出身のジャーナリスト、作家で、1920年代にはパリを訪れ執筆活動をしていた女性。お世辞にも恵まれた生い立ちではなく、性被害に遭った過去をも持つが、本人がバイセクシャルであることやボヘミアン生活をしていたことなどで人生経験が桁違いであり、それを文学に反映することで豊富な層が生まれ厚みとなる。日本ではあまり馴染みのない名前だが、彼女の豊富な人生、ぜひ覗き見してみたいものだ。
映画の中では、ギルと一緒に踊るシーンにて後ろ姿のみ出演。
サルバドール・ダリ

スペイン生まれの画家で、シュルレアリストの代表的な人物。幼い頃から絵筆を握りキャンバスと向き合っていたダリは探究心が強く、絵画手法はなんでも試していたようだ。過去の絵画表現法の流派であるポスト印象派やキュビズムなどのタッチの作品を残してもいる。ダリの作品で代表的なのは、時計がとろけたチーズのように柔らかく垂れ下がっているのが印象的な『記憶の固執』。硬いものと柔らかいものをひとつの絵の世界に(歪に)共存させ、見る者の不安と欲求を引き出す、まさに現実を超越した作品を生み出すのがダリだ。
映画の中では中盤を過ぎた頃に登場する。「私はダリだ」と何度も連呼し、自分がハマっているサイの話を一方的にずっとしているが、ダリは自己愛が強いのも特徴だったそうで、それをよく表しているかのようだった。ちなみに、サイに心酔していたエピソードは事実で、ツノに美学と哲学を感じてやまなかったダリは、たびたび自身の作品にも取り入れて描いていた。
ルイス・ブニュエル

スペイン出身の映画監督。シュルレアリスムやエロティシズムを徹底的に追求した作風である。サルバドール・ダリと交友が深く、1920年代後半に短編『アンダルシアの犬』を合作した。
ブニュエルの代表作『皆殺しの天使』は、20人のブルジョワジーが屋敷で晩餐会を楽しむ夜、宴も終わったのに誰も帰ろうとせず誰も部屋から出られず、やがて人間の本性が剥き出しに…、といったストーリーだ。映画では、そのプロットを2010年を生きるギルがブニュエルに教え伝えるというシーンが終盤にある。突然意味のわからないことを言われたブニュエルは「なぜ帰らないんだ?」と繰り返すが、後にあの『皆殺しの天使』が作られたきっかけになるとは…というジョークを差し込んでくるセンスは嫌いじゃない。
マン・レイ

アメリカ出身の写真家。20代前半の頃までは画家として活動していたが、パリ渡ったのを機に本格的に写真へ取り組む。またマン・レイは、シュールレアリスムの前身ともなるダダイスト(第一次世界大戦下で、反戦を主張し伝統的芸術を覆す運動で、世界的に広まった)としても知られており、ニューヨークで<ニューヨーク・ダダ>運動に積極的に参加していた。パリへ渡ると、ダダの派生型シュルレアリストであるダリとも交流を持つこととなる。多くの著名人のポートレート、アートフォト、ファッションフォトを手掛けてきた。
T. S. エリオット

イギリスの詩人、批評家。映画では、何度目かのタイムスリップの際にいつものクラシックカーに乗車しており、ギルがその名前を聞いてテンションが上がるといった短いシーンで登場する。ほとんどをイギリスで過ごした彼は、パリに滞在していたのは束の間のことだった。非常に勤勉でハーバード大学を出、ソルボンヌ大学、マールブルク大学、オックスフォード大学にも通い哲学を学んでいた。
アンリ・マティス

フランスの画家。原色で色鮮やかに彩り、大胆に踊るようなタッチの画法であるフォーヴィズムのリーダー的存在で、色彩の魔術師との異名をもつ。マティスの絵は、同じく色彩の魔術師と呼ばれるラウル・デュフィなどに大きく影響を及ぼした。時代や顧客の変化に合わせて絵のタッチも柔軟に変容してきたマティス。グラフィックデザインも手掛けてきたという史実もある。
映画では、ガートルード・スタインが500フランでマティスの絵を買おうとしているシーンが流れた。日本円で言うと今のレートで約6万弱だろうか。夢のようで…
ここからは、さらに過去を遡り1890年代へ。映画では、ギルがアドリアナと馬車でタイムスリップした先のレストランで以下の3人の男たちと出会う。
アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック

フランスで生まれ育った後期印象派の画家、イラストレーター。シルクハットと低身長が特徴のロートレックだが、少年時代に両足を骨折したことで下半身の成長が止まり、成人しても身長は150cmに満たなかったほどだったという。20代にパリでゴッホらと出会い、共にグループ展をしている。
ポール・ゴーギャン

フランスの画家。元は証券マンだったが、自ら絵を描き始めたのは20代半ば頃、カミーユ・ピサロの元で教わったのが最初で、本格的に絵画に取り組んだのは30代も過ぎた頃だった。ゴーギャンは生涯でたびたびタヒチを訪れているが、彼の作品には色鮮やかな原色使いや力強いタッチにその経験がよく現れている。ゴーギャンといえば、一時期ゴッホと暮らし、共に作品作りをした仲としてもよく知られている。
エドガー・ドガ

フランスの写実主義の画家。バレエの鑑賞を好んで嗜んでおり、バレエを題材にした作品を多く手掛けていた。『ミッドナイト・イン・パリ』では、服飾を学ぶアドリアナに「友人が、バレエ衣装を手伝ってくれる人を探している」という話を持ちかけている。
さて、至極著名であるモネやゴッホは、ほのめかされてはいるものの映画の中に人物として登場はしない。
モネはストーリー冒頭のモネの庭や、中盤の博物館内で水蓮の絵画を紹介されており、ゴッホは本作のキービジュアルの絵画タッチに取り入れられている。
ちなみに両者とも、ギルとアドリアナの2人がタイムスリップした1890年代にはどうしていたか。その頃モネはジヴェルニーに作った<水の庭>にてアトリエを構えて制作に夢中な頃だった。一方のゴッホはというと、ゴーギャンとの共同生活はすでに破局しており、1890年の7月、37歳の若さでこの世を去っていた。史実に沿って作られた映画だと改めて気付かされたのと同時に、もう10年ばかり早い時代にタイムスリップしていれば、ギルたちはゴッホとも対面していたかもしれない、と思うとまた別のロマンを感じる。
おわりに。
パリの美しい風景に酔いしれて、登場する芸術界の偉人たちを気軽に楽しめる映画だが、「アートや文学は好きで興味はあるけどにわかだ」という人の知的探究心は思いっきりくすぐられるだろうと思う。
私はアートや読書そのものは好きで、美術館にはよく足を運び本を読んだりもするが、芸術家・作家の名前や西洋美術史に詳しくもなんともなく、ただ表面だけをさらっているだけの人間だ。『ミッドナイト・イン・パリ』を視聴して多くの芸術家の名前を知り、今回この記事を書くにあたってこれまた浅い部分だけではあるが、1920年代パリを中心としたアーティストたちの知識を頭に入れられたことはとても有意義な時間だった。
「展示会に行ったことのあるあの著名なアーティストたちは、生きる年代が一緒で、しかもパリで交友があったのか!」
「ギルと出会った時期、ピカソ、ダリ、ヘミングウェイ、etc… は彼らの人生のうちのこの期間だったのか!」
という知識を入れた後に再度視聴すると、尚更に映画がおもしろくなる。前項でも少し触れたが、そこかしこに人物や作品にまつわる逸話(小ネタ)を入れ込んでいるのにも気付くと口元がゆるむ。
パリの景色、<黄金時代>という憧れ、著名な偉人たちの登場… 多方面からのアプローチがされている作品なので、何度観ても新しい発見があり、観る度ごとに好きになっていく、そんな素敵な映画だった。
それではまた次回まで。